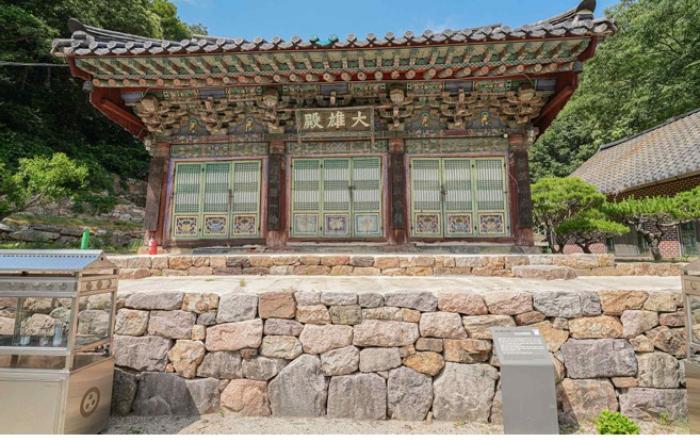宗教弾圧と戦争協力
【神国」思想】
●吾が皇統の万邦むひなることを道破して――大日本は神国なり。天祖肇めて基を拓き日神長く統を伝え給う。吾が国のみこのことあり。異朝にはその類なし。この由に神国というなり。――(国民精神を統一するために編まれた『国体の本義』)
-----------------------
大日本帝国は神国なり。ある年代の人々はこれを史実、当然のことと受け止めました。これは北畠正親の「神皇正統記」からの引用で人々の脳裏にはひたすら、「我が国は神国である」と刷り込まれたのです。日本が本当に神国かを問うたり、天皇制を検討することなどはタブーでしたから、神国論を批判した文献などこの時代には皆無でした。(<2002年度 カトリック社会問題研究所夏期セミナー>)
●肇国(国の初め)、大日本帝国は万世一系の天皇、皇祖の神詔を奉じ永遠にこれを統治し給う、これわが万古不易の国体である。而してこの大義に基づき一大家族国家として億兆一心聖旨を奉戴し、よく忠孝の美徳を発揮する。これ我が国体の精華とするところである。国体は我が国永遠不変の大本であり、国史を貫いて柄として燦燦と輝いているものである(『国体の本義』)
-----------------------
このような皇国史観がすべてをがんじがらめに規定して、それを疑うことは絶対に許されなかった時代。天皇制、国体、国家神道など天皇がらみの概念はタブーであって口に出すことさえ控えなければならないとされました。お国のため、天皇のために滅私奉公することは当然の義務――少なくとも表向きはそのような建て前で国全体が動いていたのでした。(同)
【宗教団体法制定】
<アメとムチの法案>
宗教団体法の原型となった「宗教法案」が最初に登場したのは、明治22年(1889年)のことだった。第14回帝国議会に提出されたもので、時の総理・山県有朋は次のように法案の提出理由を述べている。
「国家ハ信仰ノ内部二立入テ干渉セザルコトハ勿論ノコトデアリマス。併シナガ
ラ其ノ外部二現ハルル所ノ行為ニツキマシテハ……国家ハ之ヲ監督シテ社会ノ秩
序安寧ヲ妨ゲズ、又臣民ノ義務二背カザラシメントスルコトハ、是レ国家ノ義務
デアルノミナラズ、又其ノ職責二属スルモノト存ジマス」
と述べ、続いて提出理由は宗教団体への恩典の数々を並びたてた内容だった。「兵役の特典」「租税の免除」等々。要するに、監督管理する代わりに、特典が与えられるアメとムチが中身だった。
宗教側はこれに乗るか乗らないか、どう対処したのか。じつは乗らなかった。特に仏教界が強く反対した。
大日本仏教同盟会が出した「反対意見書」は第1に、「(宗教団体の)自治の権能をほとんど認めていない」と突っぱねた。
法案によれば、寺・教会・教派・宗派などの宗教団体は、主務官庁(文部省など)の「監督」に属し、主務官庁は「報告」を徴し、「検査」し、必要な「命令」を発し、または「処分」ができる規定になっていた(第14条)。
なんだか昨今の宗教法人法改正に際しての争点がそのままみたいなのだ。
しかしともあれ、仏教団体などの動きもあって、法案は否決され消えていく。
<宗教団体法の誕生>
次に、第2次宗教法案が提出されたのが昭和2年(1927年)。第1次法案から30年を経てのことで、しかしこれも審議未了で日の目をみなかった。
この後は、いよいよ「宗教団体法」と名称が変わり登場。昭和4年(1929年)の第1次宗教団体法案に次いで、同14年(1939年)第74回帝国議会に再度提出され可決。翌15年(1940年)から施行された。
宗教団体は主務官庁の「認可」制。認可を得ないでは設立、規制の変更、法人になること、合併・解散ができない――といった内容だった。
しかも昭和に入ってからの第2次宗教法案以降は、仏教界も積極的な法案推進に転じていた。仏教連合会が推進大会を開くなど、神道教派とともに「1日も早い成立」を陳情、請願した結果であった。
【治安維持法】
●国体を否定し、神宮または皇室の尊厳を冒涜すべき事項を流布することを目的として、結社を組織したるもの、または結社の役員その他指導者たる任務に従事したるものは無期または四年以上の懲役に処し、情を識りて結社に加入したるものまた結社の目的遂行の為にする行為をなしたるものは一年以上の有期懲役に処す(治安維持法)
-----------------------
この法律から新聞紙法や出版法などに至るまで、当時一般的な報道の規制を目的として取り締まるための法律は、電信法まで含めると26の多きに及びました。つまり、天皇制の下に言論の自由などは望むべくもなかったのです。
もちろん、信教の自由についても事情は同じでした。新憲法の下で言論の自由や信教の自由が保障されているはずの今日でもなお、皇室の存在は時としてマスコミに沈黙を余儀なくさせます。カトリックの代表的ジャーナリスト、酒井新二氏の著作には「天皇制に抵触すると宣教できない」とか「(天皇制については)マス・メディアさえ沈黙している」といった事例が挙げられています。(<2002年度 カトリック社会問題研究所夏期セミナー>)
自らを「超宗教」の高みに祭り上げ、他の宗教は国家神道を侵さない限りにおいてのみ存在を許す、という排他性・偏狭さが実際だった。(同)
【戦争協力】
終戦直後、憶えておられる方も多いと思いますが、東京・九段の靖国神社周辺や皇居前広場には、敗戦を詫びる人々の姿がありました。食うや食わずの困窮をものともせず「天皇さま、奉公心が足りず申し訳ございませんでした」「私たちの努力が足りませんでした」といつまでも頭を垂れている姿があちらにもこちらにも見られました。そのように教育したのは国家神道であり国粋主義者だったわけで、今日を生きる私たちの目から見れば、そのように教育された人々は国家神道の犠牲者、15年戦争の被害者です。家を焼かれ人生を破壊され肉親を奪われながら、まさに被害者が加害者に「申し訳なかった」と詫びる構図をもって、国全体を統治していたのです。(<2002年度 カトリック社会問題研究所夏期セミナー>)
ところで、かくして成立した団体法の結末はどうであったか。にわかに起こった教派・宗派の統合の嵐であった。同法施行後1年以内に文部大臣の「認可」を受けないでは存立できなかった。その結果、従来の仏教56派は28派に、教派神道13派はそのままだったが、キリスト教の新教は合同し日本基督教団など2教団となり、すべり込みで認可を受けた。この辺は周知の通りだ。戦時下のことで、昭和16年(1941年)6月には第1回宗教報国大会。大東亜戦争に入ると各宗派は競うように「戦時布教方針」をたて、勤労報国隊や軍費献納運動に走った。各宗教宗派の独自性とヒューマニズムは見失われ、戦争協力の翼賛宗教に転落していった。みんなが知っているところだ。
単純に歴史が繰り返すなんてことはだれも思わない。とはいえ、「歴史に学ぶ」とはどういうことかとつくづく思わざるを得ないのである。(『月刊住職』H8.4)
<大分県仏教連合会の宣言>
◆今次の支那事変たるや、東亜の安定と世界の平和とを 以(もっ)て国是とする帝国一貫の皇道を妨ぐる支那軍閥を膺懲(ようちょう)して、これが反省を促し、万邦協和の理想世界を建設せんとするに外ならざることは、多言を要せざる所なり。……我等生を皇国に受け、教を仏陀に奉ずるもの、勇往邁進(まいしん)報国報仏の大業に躍進すべき秋なり。ここにおいて我等は、仏教連合会を創設し、緊密なる連携協調の下に、大菩薩(ぼさつ)道の法旗を高揚し、精神報国の大運動を起し、上聖明に対(こた)へ奉り、下国民精神総動員の実績を挙げ、以て仏徒の本分を尽さん
-----------------------
宗教団体による戦争協力の論理は、12年11月別府市の西本願寺別院で開かれた大分県仏教連合会(会長 奥大拙)創立大会での宣言に、その一例を見ることができる。(<戦時下の宗教統制>070620)
<日蓮宗>
1915年(大正4)の大正天皇の即位大典に際して、日蓮宗宗務院は、偽作である「奉献本尊(蒙古調伏護国の本尊)」を宮内庁に献納するのだが、その解説を清水梁山に依頼し、「日宗新報」奉祝記念号を特集して、梁山筆の「奉献本尊玄釈」「同開光文」「同説明書」を発表する。
「奉献本尊玄釈」に解説されたその内容は「王仏一乗即神仏一体にして聖天子即是本尊の正体、霊山虚空即高天ヶ原、宝塔即高御座、二仏並座即是両陛下、故に法華経即大日本国の説明也。寿量本仏即聖天子也。」というものであった。(<教化情報第12号「現代教学への検証」>070620)
昭和に入った1928年(昭和3)6月に開かれた「天皇即位御大典記念日本宗教大会」では、仏教、基督教、神道関係者が集まり、国体明徴をめざして「皇道仏教」という言葉が広く唱えられるようになっていった。
この場合の皇道仏教とは一般的な意味で、国体の本義(日本が記紀神話に基づく天皇中心の国であること)を明徴にするために、「皇道」を扶翼して国民を教導する仏教のあり方という意味だろう。(同)
1938年(昭和13)には各地の寺院で戦勝国祷会・戦没者追悼会が開催され、五月に宗務院は国民精神総動員・立正報国運動の促進を通達している。(同)
1915년(타이쇼 4)다이쇼 천황의 즉위 대전에 있어서, 니치렌종 종무원은 위작인 "봉헌 본존(몽골 조복 호국의 본존)"을 궁내청에 헌납하는데, 그 해설을 시미즈 량산에 의뢰하고"니쯔슈 신보"봉축 기념호를 특집으로 하고, 양산 붓의 "봉헌 본존 현석""이 개광문""이 설명서"를 발표한다.
"봉헌 본존 현석"에 해설된 그 내용은 "왕불 이치 죠우지 곧 신불 일체에 성 천자 곧 이 본존의 정체, 영산 허 공즉 고천케원, 보탑 즉 옥좌, 두 부처 병좌 즉 이 두 폐하, 고로 법화경 곧 대일 본국의 설명이오. 수량 모토 즉시 성 천자이다."라고 하는 것이었다.(070620)
쇼와에 들어간 1928년(쇼와 3)6월에 열린 "천황 즉위 미사 대전 기념 일본 종교 대회"에서는 불교, 기독교, 신도 관계자가 몰리면서 국체 명징을 목표로 "황도 불교"라는 말이 널리 주창할 수 있도록 되어 갔다.
이 경우의 황도 불교는 일반적인 의미로 국체의 본의(일본이 기키 신화에 기반한 천황 중심의 국가임)를 명징 하다 때문에,"황도"을 보필하고 국민을 교도하다 불교의 현 주소라는 뜻일까.(이)
1938년(쇼와 13)에는 각지의 사찰에서 전승국 도회, 전몰자 추도회가 개최되어 오월에 종무원은 국민 정신 총 동원, 릿쇼 보국 운동 촉진을 통보했다.(이)
<浄土真宗>
大谷光瑞は1931年の満州侵略を唱讃し、仏教徒が正義のために戦争することを肯定した。また、1938年の国家総動員法が公布されるに当たって、宗教報国運動を展開した。本願寺派の梅原真隆は『興亜精神と仏教』を刊行し、聖戦論を主張した。また、1942年には金子大栄が『正法の顕現』を著して、誓願に基づく聖戦であることと、仏法が神道の一部であることを主張した。同様に、清沢満之門下の暁烏敏も『臣民道を行く』で、戦争を擁護している。1943年には、龍谷大学興亜科の普賢大円が、『真宗の護国性』を刊行して、天皇絶対主義の思想をそのまま真宗教学として位置づけ、神道と仏教の相互補完を説いた。この傾向は、1945年の大谷光照法主の『皇国護持の消息』、本派の『宗門決戦綱領』、大派の大谷光暢法主の『殉国必勝の教書』でその極に達する。(<kenkyukou>070620)
戦争という時代背景の中、私たち念仏者が真宗教団として選択したのは「戦争協力」という道でした。1941(昭和16)年、太平洋戦争に突入するにあたり、『本願寺新報』(本願寺の機関誌)では、教団挙げて臨戦態勢の強化を強調する記事を掲載。仏具供出、戦時布教、戦時教学、その後兵器献納、日曜学校における献金運動、宗教戦士として各地に出兵しました。「皇国の宗教としての浄土真宗」と自ら名乗り、聖戦の名のもと、国家の戦争遂行に積極的に協力したのは、隠すことのできない事実なのです。(<真宗教団の戦争協力>070620)
<臨済宗妙心寺派>
●太平洋戦争。同派は全国の信徒から資金を集め戦闘機を国に奉納した。機名は「花園妙心寺号」。仏は不殺生を説く。時代のすう勢とはいえ、教えを破ったことに変わりはない。(河野太通=花園大学長/<神戸新聞>WS掲載日:2003/08/10)
●高校教師をやめ、父の跡を継いだ。ある日、自宅にあった宗派の機関紙を読んだ。「興禅護国」「宗教報国」。戦争協力と戦闘機献納への道のりがあった。(水田全一住職/同)
<真言宗>
昭和18年には「真言報国団」の名前で陸軍に飛行機を献納している。(<陸軍愛国号献納機調査報告>WS070623)
<キリスト教>
自らを「超宗教」の高みに祭り上げ、他の宗教は国家神道を侵さない限りにおいてのみ存在を許す、という排他性・偏狭さが実際だった。国粋主義一辺倒となった昭和前期から戦時中にかけて、唯一・絶対の神を信じるキリスト教はもっとも鋭く国粋主義と対峙する要素を持っていたわけですが、そのキリスト教がほとんど全部、雪崩を打って国家神道の軍門に下ったのでした。(<2002年度 カトリック社会問題研究所夏期セミナー>)
この時期に教会は、「超宗教(国家神道)の受容と信仰の自由は両立できるか」「神社参拝による国策協力、宗教報国による戦争完遂に励んでよいのか」という難題に直面し、いずれも受け入れました。積極的に協力する道を選択したのです。その選択をしたことについて、敗戦後50年以上経った今日に至ってもまだ、根本的反省を表明せず当時の見解を公式には撤回していません。(<2002年度 カトリック社会問題研究所夏期セミナー>)
昭和期後半のキリスト教界は、昭和16年12月の太平洋戦争突入、20年8月の敗戦、27年4月の平和条約発効(独立回復)など政治動きに影響されるところが多かった。苦境に立った教団日本基督教団の成立半年後、日本は太平洋戦争に突入、教団はきびしい戦時下の要請にいかに対処して行くかという苦しい立場に追込まれた。軍事政府と憲兵がキリスト教は国体に反するとして圧迫の挙に出たので、全教会と全信徒とを保護することは容易でなかった。教団が国策に追従し過ぎ、自信を欠いた動きをしたとしても、止むを得なかったと見るべきであろう。(<日本基督教団の成立>)
教団では開戦前から基督教報国団を組織していたが、開戦後はこれを強化し、地域の防災、託児、国債割当など戦時緊急事項の処理に協力した。一方文部省からの要請により、教師たちに大東亜における日本の使命を理解せしめるために練成会を開いた。「日本的基督教」が好んで口にされるようになったのはこのためである。教団は中国、フィリピン、インドネシア等に多くの教師を送り、現地の教師信徒との交わりを深めた立教団はまた文部省の要請により、戦時布教指針を発表したが、それは宗教報国、日本基督教の確立を骨子とするものであった。(同)
기사출처 : http://sudati.iinaa.net/senjika/kyouryoku.html
<저작권자 ⓒ 한국역사문화신문, 무단 전재 및 재배포 금지>
유시문 기자 다른기사보기